谷の鶯
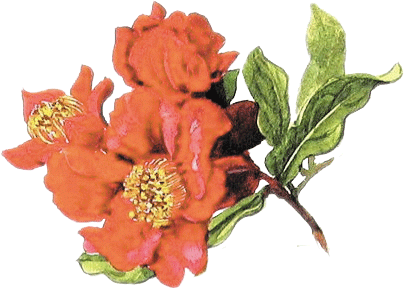
| いつの頃からだったろう。人の名のあとの括弧の中に並べられた数字、ダッシュの両端の二つの数字が妙に目にとまるようになったのは。 このあいだまでは生きていた人、もっと前に死んだ人、遙か遠い歴史の中の人。どんな死者の場合にも、生年、没年をつい確認して引算してみたくなる。それは誕生日を迎えてからか、ではなかったか? わかるならそのあたりも確かめてときには一つ引き直す。出た答を父の享年と比べたのはもうかなり昔の話で、今では、自分自身の年齢と比べては下か、上か、そこまであと何年かと思う。 この数年は、震災とそれに続いたいろいろを見ずに死んだのか、ではなかったかもまた気にかかる。 ──たとえば? 丸谷才一は今の私より二十数年長く生きて死んだ。中村勘三郎は私より六歳若くて死んだ。二人とも、あの震災の翌年の誕生日を迎えてから死んだ、続くいろいろはたぶんそれほど見ないうちに死んだ、等、等。 丸谷才一は、その年の十月初めに入院し、同じ月の十三日に心不全で亡くなった。勘三郎は、食道癌が五月に発見されて七月に手術を受け、九月に入ると、抗癌剤使用の影響から重篤な肺の疾患を発症し、十二月の五日に亡くなった。ICUで治療中との発表は前月中旬のことだったから、おそらく役者は敬愛する作家の死は知らず、作家もまた、 「君と同時代に生きられたことは誠に幸せ」 と書き送るほど、その芸と人となりを愛していた役者の死は知らずに死んだ、手術の成功と復帰をたぶん信じたままだった。かなり経ってからことの前後を確めてそう思ったら少しほっとした。好きな役者だった、何度かは舞台も見たというだけの縁であってさえ、近い身内が死にでもしたようにしばらくは落ち込んだのだ。できれば知らないままで──と願う程度には、博覧強記で軍隊嫌いのこの作家も私はなんだか好きだった。 いい読者ではなかった。肝腎の小説は二十余年前、二つほどを一度ずつ読んだきりだった。ただしエッセイ、対談の類いなら相当な量を読んだ。手もとにも文庫本で十冊余りあり、どれも、あらかたを忘れるまで寝かせておいてはまた手にとった。その繰り返しが不思議とよく利く本で、読むものを切らしたときには大いに重宝していた。 四、五日前に、さすがに補充をする潮時かと思い、近所の古本屋を三軒回ったが、未読のエッセイはなく、しかたなく目に入った『横しぐれ』を買った。これが案外面白かったから、次の日は『笹まくら』を買ってきた。どこかがなんだか私の作家ではない。その印象自体に変わりはないもののやはり面白くは読んだ。 えっ、と驚いたのは、小説それ自体とはさほど関係ない話でだった。『笹まくら』の方の、主人公の徴兵忌避の動機についての、多少自虐的な内省中の、 「おれはあのビンタ……日本陸軍名物の私刑が厭なばかりにこんなことをしたのじゃないのかと、何度も自分に訊ねたものだった。厭なのは往復ビンタじゃないのか? 鶯の谷渡りじゃないのか?」 その最後の部分に関してで、陸軍、鶯の谷渡りですぐ検索してみると、 「旧軍隊で横行した私刑の一つとして有名。寝台、または机を並べ、鶯の鳴き真似をさせながら越えたり潜らせたりさせ続けることで、屈辱感、及び身体的な苦痛を与える目的で行なったもの」 大体、そんな意味の説明がいくつも出てきて、 (これか、あの言葉って……。でもこんな偶然から、それも、三十何年も経ってわかるなんてね?) 一瞬ついわくわくとはしかけたものの、よく考えればわかって嬉しい種類の答ではなく、よく考えてみればわかって嬉しい種類の答ではなく、わざわざ電話をしてまで人に伝えたい答でもない。あの件を姉がまだ憶えているのかどうかも知らない。母はかなり以前からすでに惚けていて、もうどんなこともそう記憶はしていない。 一九一四年に生まれた父は、八二年に死んだ。誕生日の五ヶ月近く前のことだった。 病気らしい病気はしないできていた人が、その年の初め頃から疲れやすくなった。春にはまだテニスの試合もしていたが、連休には腹部が腫れて寝たり起きたりの状態になり、梅雨の前に入院すると、そのまま出てこなかった。入院から二日目に、母と姉と三人で主治医の説明を聞いた。腹水をとってみましたが、と穏やかな様子のその医師は言い、床の壜を指差すと、横に首を二度振った。一抱えもありそうな壜の三分の一ほどまでを赤暗い液体が満たしていた。傾きはじめた日に透けて、それはイチゴシロップに少し似て見えた。 イチゴシロップは、子供の頃は、夏にたまにだけ飲ませてもらえる貴重品だった。名の果物とは関わりのない、ただの色つき、香料入りのむやみと甘い液体で、その甘味だって当時のことで、チクロかサッカリンが大半だったことだろうが、五つ、六つの私にはそれが無上の美味だった。 あの頃私たちがいた町の夏の祭では、年少の子は夜の七時には家に帰されるのが決まりだった。さすがにかわいそうということだったのか、帰る前には、水割りのイチゴシロップを一杯ずつもらえることにもなっていた。姉と手をつなぎ、長い列に並んで待つあいだ、私は、台の上の壜とコップをうっとりと眺めていたものだった。アセチレンランプに透けて、濃い桃色のガラス玉のように光るシロップ、メロン、パイナップル、房のままのバナナの絵が豪奢に描かれたラベル、壜を包むあのセロハン──一面に白いレースの模様が刷られているセロハン。 進行性の、末期のという言葉を耳では聞きながら、そんな光景を私は執拗に目で追っていた。半ばは無意識のうちの方便、または、遁身の術の類い。そう、消えるのはいつも私の得意の技だった。ここにいるけれど、ここにはいない。心は、こんなことは起きていない時と別の場所にいて、だからシロップの匂いも仄かにはする、耳の奥では、笛太鼓もかすかに鳴っている。家に帰っても遠くからまだ聞こえてきた東京音頭、それだけは集会所で習って踊れた炭坑節の、月ガ出タ出タ月ガ出タ、三池炭鉱ノ上ニ出タ。あの頃は父は四十をいくつか出たぐらいの年で、黒々とした髪が痩せた顔にはうるさいほどまだ多かった。 三十を過ぎたばかりの私には、人の死は、まだいくらかはアクシデンタルなもののように見えていたが、そのときにはくるべきものがきた、とうとうとしか思わなかった。それほど長くは生きない人だという気がなんとなくして、かなり前から私は身構えていた。理由はとくになく、強いて言えばあまりに善人過ぎて、どことなく儚げだった。 父は、入院中も処置や介護の一々に常に敬語で謝意を述べ、家族には過去の些細なできごとの一々を口に出して謝った。昔、一度、勝手な思い込みで手をあげた、あれはじつにすまないことだったと頭を下げて言うのは、生意気盛りの私の言葉につい腹を立て、掌で頭を少し押したという程度のことなのだった。抗癌剤服用で初めて食欲の不振を経験すると、お母さんにも、良子ちゃんにも、食べなさいとよく言っていた、あれも、今思えばすまないことだった、 「食べないから体力がつかないとばかり、その気になれば食べられるものだとばっかり思っていてね。──食べられないものだったんだねえ、ほんとうに」 しみじみ納得したといった様子で言い、うるさく思ったことだろうねえとまた謝った。 だるくていらっしゃるのでしょうねえ、と看護師の言う言葉にも、考え考え、 「よくわからないんですよ。これがだるいということだかどうか。その経験が今まで、私にはなかったものだから」 すみませんねえ、と卦体な返事をしていたほどに、病気の前の父は丈夫な人だった。少なくとも、体の苦痛を感じることのひどく少ない人であり、存在自体が微妙にユーモラスな人なのでもあった。見舞に行けば相好を崩して迎え、部屋の彩りにと持参の水彩画を壁にかけてみれば、 「この娘が描きました」 喜色満面で来る人、来る人に告げるのだから、照れくさい点、治る見込みがない点をのぞけば、家族にとって楽なことこの上ない病人だったのだ。 当初の説明通り父の病勢は駆け足で進み、意識の混濁がじきに始まった。夢の内外を出入りするようにも傍からは見え、外にいる時間は日に日に減った。そこから肝性昏睡に入るまで、一週間ほどはあったか、それとももっとだったか? 記憶はもうずいぶん曖昧になってきているが、あのノートが病室に置かれた時期なら、父が昏睡に入る四、五日前ではなかったか。 ふと意識が戻ったようなとき、洩らした言葉を書きとどめるためのもの。そう聞いたのは姉からだったか、母の方からか? それも忘れたが、どちらにしても母の考えではあった。 当時は告知はまだ一般的ではなかったし、なにより、父はかねてから癌を格別に怖がっていた。稀にしかひかない風邪をひき、慣れぬ頭痛にあたふたすると、 「脳の癌かも知れない」 などと言ったりもした。突き指なら骨の癌、物貰いなら目の癌。一応冗談ではあるものの、 (あらかじめ、これぐらいに言っておけばかえってならないのでは) と願っているらしい気配がどこかにはあった。父の些細な頼みごとを私がつい断ったりすると、 「癌で死んだりしたら、ああ、あのときに聞いてあげればよかったと、深い後悔を……」 ともふざけてよく言ったりしたが、これにもまた魔除けの呪文めいた気配がなんだかあった。父にとって、癌は死そのものの、自分も含めて、人がいつかは必ず死ぬことの象徴だというようにも見えた。そのことがたぶん、正視できないほど怖いのだった。 肝硬変だったとだけ父には伝えられ、無論、もって一月といわれた余命の件は伝えられなかった。これもまた母の考えによることだったが、あとになって、多少の迷いが生じてもいたらしかった。父の病人ぶりのある意味での見事さに、 「私にはあれはできないわ」 と感嘆はしながら、 「子供の病人ならね、言うことはない。でも違うでしょう? お父さんは、残る私の気持にまでは、気が回らない」 そう洩らすこともときにはあった。 「辛い現実からは、目を逸らすようなところのある人だから」 とも言ってからたぶん後悔し、そして結局は、告げなかった自分の責任なのだから、治るつもりでいてくれた方がいいことなのだから、となんとか納得したがっていた。そのように私には見えた。ノートはそんな母の気持の揺れに対応するもの、生きるよすがとなりそうな言葉でもあれば、という願いによるものだったような気がするが、置く時期が遅過ぎた。なにかを聞いた、書きとめたという記憶は私にはなく、目にしたわずかな書き込みも意味がとりにくい片言、隻句ばかりだった。 何日めだったか、「鶯の谷渡り」と書かれているのを見たときはちょっと驚いた。およそ、父には似つかわしくない言葉に見えたからだが、母も姉も、この言葉の──かなり有名な──べつの意味を知らないらしく見えることにも驚いた。 谷から谷へ、枝から枝へと飛び移りながら鳴く小鳥の意味ではたぶんなく、かといって四十八手の名でもなく、さらに猥褻なあのプレイのことなのではないか、と思うのには根拠はとくになかった。父には俳句の趣味はなく、秘かな放蕩の趣味となると、それ以上にありそうには思えなかった。もう一つのべつの意味は知らないままに、おそらくは軍隊での記憶の断片、 (見る羽目にでもなったか、セッティングの世話でもさせられて……) そんな想像をすぐにしたのは、当時愛読していたアラカンの聞き書きの本で、 「関東軍は大したものやね、芸者つきで戦争しとるんダ」 とも、 「『王道楽土』やらゆうて、エライさんは毎晩極楽、春画を眺めて長じゅばん着たのとオメコして」 などとも読んだ、その影響でだったかもしれない。アラカン、こと嵐寛寿郎は軍の慰問で中国、満州に何度となく渡り、右の感想を持った。父は満鉄職員で、大連から出征し、牡丹江で初年兵となった。そう聞いていた。 たまたまのまぐれから、軍隊での不快な記憶というのまでは当てた。それはいいが、 (なにも、最後の最後に蘇ってこなくてもいいのに) そんな記憶が、それも、そんなにまで遙かな時間の彼方から──とひどく切ない気持になってから、何年なのか、あのときからはと数えてみれば、今とあのときとの隔たりよりは、四、五年ほど遠いだけのことなのだった。 姉が去年送ってくれた、父の手書きの履歴書によれば、応召は四四年三月。父が三十二の春で、入隊期間は約一年半だった。通信兵だった、所属の部隊はすぐ内地に移動して、戦闘には加わらずにすんで、という話は母から聞いた。戦争中の父の体験は、かなりましな部類のものだった。そんな印象を私はずっと持っていた。 口数の少ない人ではなかった父からは、戦時中の話、軍隊での話はごくわずかしか聞いていなかった。 ──たとえば? 趣味のテニス用の、白いソックスの踵が薄くなりだすと、父はいつも自分で繕った。あるとき、堂に入った手つきを横から眺めていたら、 「軍隊でこれはおぼえたの」 とだけ言った。 またたとえば列車の中で、あれは埼玉か栃木だったか、どこか近県の駅を通り過ぎるときに、 「ここには、軍隊でいた」 いあわせた家族のうちのだれに言うともなく言った。このときも聞いたのはその一言だけだった。 軍歌の類いも滅多には歌わなかった。『戦友』か『討匪行』だけはたまにところどころ歌い、兵隊節なら『可愛いスーチャン』をやはりたまになら口ずさんでいた。どのときも、 「お国のためとは言いながら 人の嫌がる軍隊に 志願で出てくるバカもある」 そのバージョンのそこの箇所だけ歌ったが、いつだったか、母が、 「そんな風には思ってもいなかったのに、前からだったみたいに」 と茶々を入れたことがあった。 数学が一番好きで得意でもあった、という母は、不正確な表現を好まなかった。倫理的にひどく潔癖な性分でもあったから、多少なりとも粉飾がある表現はことに好まなかった。生来の気質には大胆、闊達という言葉につながるものもかなりあったような気はするけれど、聞くところでは祖父の教育が、潔癖の方向に母を押しやっていたように見えた。これはたぶん美的な潔癖さから、陳腐な上に実感とはずれがある、と感じられる表現も好まず、相手がたまたま家族である場合には、時として苛立ちを表に出した。 歌謡番組を聴きながら父がよく言う、 「美空ひばりはやっぱりうまいねえ」 貰い物の羊羹を口にしては言う、 「やっぱり、虎屋はおいしいねえ」 は陳腐の口(「その『やっぱり』は、いらないでしょう。聴いてうまかったらうまい、食べておいしければおいしい。それだけでいいじゃない」)。「志願で出てくるバカ」はおそらくは粉飾の口。 (私と同様、あなただってお国のためにと思ってしまっていたのじゃないの? あとになってわかったことを、前から戦争反対だったように歌うのはフェアではないわ) 少し棘のある母のからかいをそのように私は聞いた。父はとくに反論はせず、母は母で、それ以上のことは口にしなかった。一瞬の苛立ちをつい表したときの常として、ひそやかな自己嫌悪に駆られていたのかもしれなかった。 残る一つの記憶では父の反応は違った。そのときの母とのやりとりは、当時話題を呼んでいた『人間の條件』をめぐるものだった。ある場面でのできごとについて、 「あんなことは軍隊ではあり得ない」 と父が言った。言い捨てた、というのに近い口調は父にはかなり珍しく、 「それはわからないじゃない。あなたが見てきたものはそうでも、あれは小説だとしても、いつ、どこでも絶対にあり得ないとは、断言できることじゃないでしょう」 母の言うのに、即座に、 「ない、ない」 と重ねて言った、これもまた珍しかった。 話は軍隊での不服従行為に関してだった、と思うのが耳にした言葉の記憶によるものなのか、漠然とは知っていたあらましから推測してあとで足したものなのかははっきりしない。話が映画か、原作についてのものだったのかもよくわからない。映画を二人で見たあとだったという気はしているが、確信はなく、家でパンフレットを見かけた記憶もとくにない。 本は、居間の本棚の少し下の段にたしかにあった。小学生だった私はすでに重症の活字中毒で、家にある限りの本は内容を問わずに片端から読んでいた、と思うのだけれども、これは読んだ記憶がまるでなく、どういう理由でからか、好きではなかった装幀だけが妙に鮮明に今も目に浮かぶ。ソフトカバーの新書判、白地の下半分に地味な薄緑の地模様、黒の愛想のない題字──やや縦長の明朝の題字。 検索によれば、本は全六巻だとあるものの、六冊が並ぶところを目にしたような記憶もないから、母が古本屋でみつけた端本だったのかもしれないし、読書会用に人から借りていたものかもしれない。あの頃、母は知人たちとときどき読書会をしていたし、家の近くにはまだ図書館はなかった。そのはずで、二架の小さな本棚を埋めていた本の多くも、古本屋で買ってきたらしいものだった。 『人間の條件』第一巻刊行は、これも検索によれば一九五五年。全巻がようやく出揃い、時の大ベストセラーとなったのは五八年。本同様六部作の映画のうちで、軍隊での生活が主に描かれる三部、四部の公開は五九年秋だとある。だとすると、あれが映画のあとだったと見てもかなり早い時期の話のはずで、父の除隊は、たぶん、母とのやりとりを遡ること十四、五年。七つ、八つの子供には目も遥かな昔だが、今の私にはそれほど遠く思える過去ではない。 四十代半ばの父にとっては、それはどの程度の遠さ、または近さと感じられる過去だったのか、鳴き渡る鶯は、父自身の姿でもあったということなのか? たぶん大して遠くはない過去で、おそらくは父の姿ででもあったのだろう。 無論、言葉そのものはふっと浮かんできた記憶の断片、たまたま聞き取られ、書きとどめられた最後のものだったというだけで、末期の思いなのでも、父の生涯の最重要事であったというのでもない。次の瞬間には思いはすぐ別の枝、別の谷へと飛び移っていった。そんなことだったという気はするが、母が、 「お父さんたら、聖書の言葉をもう文字通りに信じてたのよ。水の上を渡っただとか、そんなのまでよ? それが除隊して帰ってきたら、もうクリスチャンじゃなくなっててね……。所詮、その程度の信心だったということだわね」 冗談めかして言っていたあんな話も、あのにべもない否定もやはり前とは少し違うもののように見え出してくる。 母は、父の軍隊経験を軽いものとして見過ぎてはいなかったのか、そもそも、話自体ほぼ聞かされてはいないのではなかったか。そして、母に語らなかったのだとすれば、父は、その時期のことは、ほぼだれにも語らないままで死んでいったのではないか? 父には、辛い現実と母が言う類いのことは、心に思うさえとても忍びない、と感じているらしい気配がたしかにあった。かつてあったこと、今後起きるのかもしれないことの、どの場合に関してもたぶんそうだった。「忍びない」は、いくらか大袈裟に言えば、父の最重要の行動原理の一つらしかった。荒い声を出す、人に手を上げる、威張る、言葉にしてしまえば身も蓋もない、といったことをわざわざ言葉にして考える、人に言う。そのどれもが父にとっては、主義主張以前にするに忍びないことであるように私には見えた。 根が楽天的だった、体は健康だったという点をのぞけば、父は、およそ軍隊には向かないたちの人であったのだと今では思う。ことに若い時分には、人からは威張られやすく、軽く見られやすいところがあった。そうも聞いていた。人におしまけない個性があった母とは、その点でも対照的だったといってよかった。 母は敗戦を大連で迎え、父の出征後に生まれていた上の姉と二人で引き揚げた。 (お父さんは、あれとくらべれば……) というような気持が母の中にはあったのかもしれず、私自身の印象もどちらかというと母の経験と比較してのもの、または母の思いを推し量ってのものだった。そんな気も今はしている。 母からは、当時の話はわりによく聞いた。ソ連軍の将校たちの、「テントのように巨大な」軍服を洗い続け、アイロンを日々かけ続けて生きのびたという話、またときどきは、夜に拳銃を持って押しかけた、酔ったシベリアの囚人兵を母一人で撃退した話。 「拳銃をつかんで、卑怯者! って言ってやったのよ、覚えたてのロシア語で。女子供しかいないところに、大の男が、そんなものを構えてきて恥ずかしくはないかって」 ブロークンなそのロシア語でときには通訳の真似ごともした、将校を相手に、『アンナ・カレーニナ』についてしばし語り合い、 「といったってなにをどう話せていたものなのか、だわねえ、今思ったら。それでも、こんな話ができるのは久しぶりだって、ずいぶん喜ばれてね。兵隊はほら、字も読めないような人が大半だったんだから。トルストイどころかよ。もう信じられないほど無知で、でも、善良といえばとことん善良で、みたいなね?」 そんな兵士たちのマスコットであったと聞く姉は、引き揚げから一年足らずで病を得て死んだ。三歳の誕生日の約三ヶ月後のことだった。母が苦労した、辛い目にあったという印象は主にその結末からくるもので、子供の耳には、話の全体はどちらかというとロマンティックな冒険譚に似て聞こえた。 母の性格には、平坦な日常よりは非常時の方に向く面がどこかあったし、生得の語学能力に加えて、人の目を惹くに足りる容姿の持ち合わせもあった。そのどれもが、むしろ災いの元となることも十分あり得ただろうが、 「まあ、よくされた方というんじゃないの? ある意味、特別扱いだったというか」 それもまた、十分にあり得る範囲のことと思えた。たしかに、母はいつでも周囲からは不思議なほど「特別扱い」にされやすかった。屈辱感の類いはとくに味わわずにすんだとしても、それもあり得ることだったという気が私にはした。だからたぶん、父よりは語りやすかった。 語らずにはいられない事情もおそらく母にはあった。姉は敗戦前年の四月に生まれて、引き揚げ直後に発病して数ヶ月で死んだ。片言をやっと話し出し、まだ元気で生きていた短い月日は、侵攻から帰国までの月日とほぼ重なり合っていて、姉についての記憶をほかのできごとと分けて残すことはおそらく難しかった。その月日の記憶を共有する相手を身近に持たなかった母は、語ることで、姉がたしかにいたのだと確め続ける必要、少しでも長く、「今、ここ」に生かし続ける必要がたぶんあっただろう。短かった姉の人生の短い盛りのその時期、その場所に父はいあわせなかったし、大連での知り合いは、戦後は皆散り散りにそれぞれの郷里へと帰っていた。 母の努力は無駄ではなかった。会うことのなかったこの姉は、聞いた物語を通して私の記憶に長く棲みつき、母が忘れ去った今も、淡く薄れながらまだたしかに生きている。もう一人の姉の中にも、どんな形でなのかは知らないが、やはり生きているのだろうと思う。よく言うように、人は、語られることで生きた時間よりいくらかは長く生きのびるものなのだろうと思う。 母が介護つきのホームに入所したのは、三年あまり前の春だった。入所のいくらかあとに、私は母が住んでいた部屋からかなりの量の写真と手紙を持ち出していた。古い写真はすぐ修復して焼き直したが、手紙の方は読みも仕分けもしないままで長らく放置していた。 ざっとだけ見て、母の知人たちからのものばかりと思い込んでいたのだが、つい最近手をつけて、父からの手紙も交じっているのに気がついた。 一九七二年の七月に、父は簡易保険局を早期退職し、簡保保養センター事務局長となって那須に単身赴任した。事前にはひどく楽観していた本人は、一人暮らしが現実となると手放しの淋しがりようで、結局、母が週一に近い頻度で埼玉から塩原まで通う羽目になった。 「話が出たときね。ほんとうに大丈夫なのって、何度も念押したのよ。お父さん、一年間だけだから、景色もいい場所だからなんて言い切って、蓋を開けたら、もう案の定じゃないの。それはまあ、家族のためなんだしね? かわいそうとも思うけど、自分で決めて行ったわけでしょう、ならもっとねえ、こう……」 疲労困憊した母は、溜息と共に言った。 それだけでは不足だったか、父は案外まめに母に手紙を書いてもいたものらしい。残る十二通はどれもその時期に那須から出されたもので、内訳は封書が七通、葉書、絵葉書が合わせて五通。 そのうちの二通の中に、私は、鳴き渡るべつの鶯を見つけた。 七三年の春も終わる頃、里から帰った鶯は木々の枝で鳴き、谷でも「絶え間無く」鳴いた。帰る夏を指折り数えて待つ父は、いそいそとその声を聞いた。 そのうちの二通の中に、私は、鳴き渡るべつの鶯を見つけた。 七三年の春も終わる頃、里から帰った鶯は木々の枝で鳴き、谷でも「絶え間無く」鳴いた。指折り数えて夏を待つ父は、いそいそとその声を聞いた。 (じつはあれは塩原の谷の鶯、十年前の春に耳にしていた、ほんとの鶯で……) とまではまさか思わないけれど、あのあとにすぐ──たとえば鶯の連想から──父の思いは那須にまで飛んだ、もう三ヶ月も待てば、と思いながら聞いた声が耳には蘇り、浮き立つような気分にも一瞬なった。そんな想像をちょっと欄外に記す程度なら、 (粉飾、というほどでもまあないのでは?) そう考えてみることにして、鳴く二箇所をここにも引き写す。。 「今日お葉書受領いたしました。 椿を植えて庭も一段と良くなった由、次に帰る日がだんだん楽しみになります。時折り古い写真を出して見ながら思い出しております。 こちらも一昨日から、昼になってから多少動き回ると汗ばむ様な気候になりました。鶯が葉のない林や森の中から聞こえております。八汐つつじもピンクの花びらが多少見えて来ました。恐らく来週あたりになると一面、盛りとなるものと思います。若葉も少し顔を出してきましたから、若し都合が良ければ来週は是非お出で下さい。 ご案じのガラスは本日入れました。ついでに食販でブドウパンを二斤買って来たから当分心配は要らない。独りの生活も淋しいけれどそれ程苦になりません。時たま暗くなって帰ると、腰を低くして出迎える犬が居ないのが堪らなく淋しいやら悲しいやらなる事もあります。 一昨日はお隣の木村さんから梅の木の小鉢植と楓の盛り植えを一つずつもらいました。毎日水をやっております。そろそろ庭の掃除でもやらないとみっともないからと考えております。 箒川の流れる水音も、昨年七月私が着任した時の流れの音に近づいて来た。早く春から夏になるとよい。 山崎家にはお礼を出しましたから(余り名文ではないけど)。 扨、時計が十一時を過ぎましたから、今夜はこれにて二階に上がる事にします。それから若し今度来る折は又川越の芋ようかんを買ってきて下さいね。みそも殆ど切れていたので持参下されば幸い。送って迄とは決して申しません。 では気をつけてお過ごし下さい。 私は大丈夫です。頑張りますから。 四月六日 みよ子様 時雄」 「食卓の上の牛乳ビンに木村さんからもらった一重の山吹が一枝生けてあるので、何だかにぎやかな感じがする。那須もすっかり春の雰囲気になってきた。前の山も衣替えでブナのみどりがくっきりと美しい。谷間から鴬の声が絶え間なく聞こえて来る。小生の植木もみどりが出てきて楽しみの一つ。 独りの生活も、閉じこめられた冬に比べると春は割合淋しさが薄くなる。それでも日高に帰る日を数えて楽しい。 今夜は上原謙の出るテレビを見てその昔をなつかしく思い出している。青春の大半を過ごしたアカシヤの大連のまちを。 予定は、三日は移転初めての西武園テニスクラブに行ってみたし。四日は、若し時間があれば入院中の楠山さん(悪い病気らしいとのこと)のお見舞いをしたい所存。五日朝の列車で那須に帰る予定です。我家に三泊出来ますよ。 扨十時になった。いざ二階の寝室へ。此の手紙と私とどちらが早く家に着くか。 ではまた。 四月二五日 みよ子様 時雄」 |